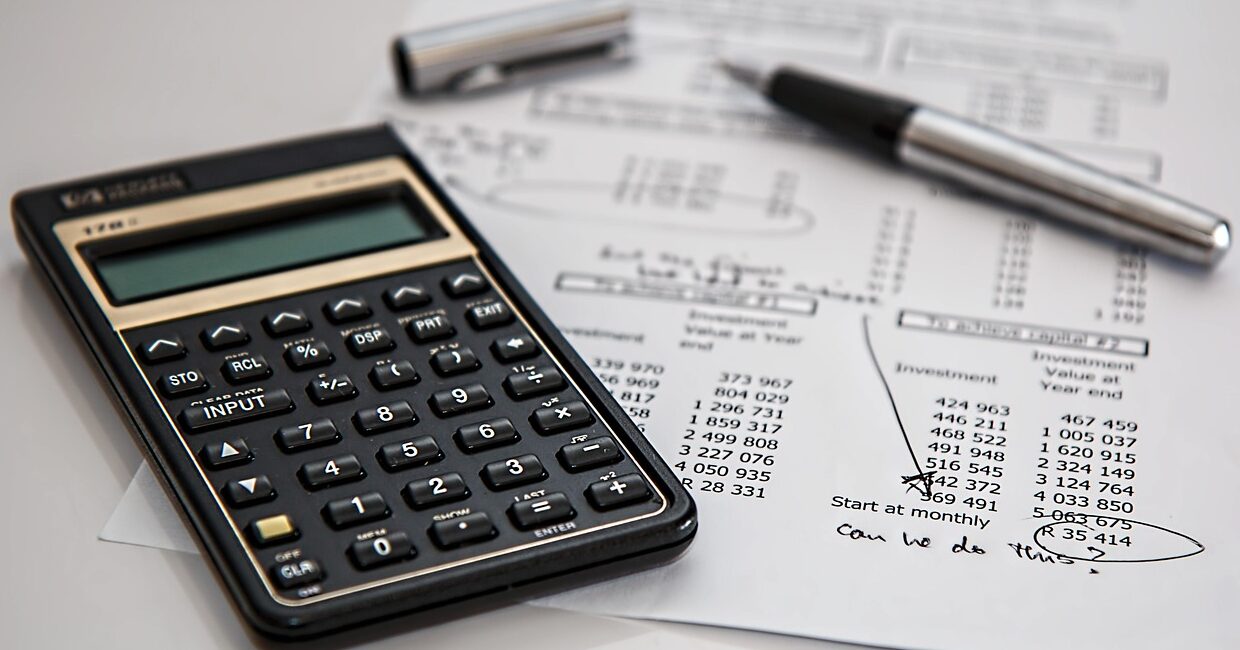注:本記事は2025年6月時点の情報に基づいて作成しています。商品やサービスの内容・料金等は変更されている場合がありますので、最新情報については各公式サイト等でご確認ください。

この記事では次のことがわかります。
・保険見直しで月2万円節約する具体的方法
・県民共済の保障内容とコスパの良さ
・保険と投資を分離する資産形成戦略
「毎月の家計が苦しくて、
老後資金の準備がまったく進まない」
そんなお悩みを抱えている
40代サラリーマンの方は
多いのではないでしょうか。
子育て世代の今は支出が多く、
老後のことまで考える余裕がない。
でも給料はなかなか上がらない現実に、
将来への不安が募るばかりです。
保険と投資が混在し、
どちらも中途半端になりがち
という問題を抱えている方は
実はとても多いのです。
私もまったく同じような状況でした。
しかし、保険の見直しを行うことで
月2万円の家計改善を実現し、
老後に向けた本格的な資産運用を
スタートできました。
「たった2万円で何が変わるの?」
と思われるかもしれませんが、
年間24万円を20年間運用すれば、
複利効果により大きな資産形成も期待できます。
実は保険の見直しは、
老後資産形成の第一歩として
もっとも効果的な方法の一つです。
なぜなら、一度見直すだけで
毎月確実に支出を減らし、
その分を資産運用に回せるからです。
特にドル型保険(外貨建て保険:ドルなど
外国通貨で保険料を運用する商品)から
県民共済(都道府県が運営する
非営利の共済制度)への切り替えは、
必要最小限の保障に絞り込むことで
大幅な保険料削減が可能になります。
浮いた資金をNISAを活用した
資産運用に回すことで、
全体最適な資産形成戦略を構築できるのです。
この記事では、私が実際に体験した
ドル型保険から県民共済への見直しを通じて、
月2万円の家計改善を老後資産運用に
集中投資する方法をお伝えします。
保険見直しの具体的な手順から、
浮いたお金のNISA活用方法まで、
純資産3000万円をめざす実践的な
戦略をご紹介します。
読み終わった後は、
ぜひ現在の保険内容を確認してみてください。
私がドル型保険を手放して県民共済+NISA戦略を選んだワケ
私が保険見直しを決意したのは、
2年前に家計の見直しを行った際、
保険料が老後資産形成の大きな足かせに
なっていることに気づいたからです。
当時加入していたドル型保険は
月額2.5万円、医療保険が月額5,000円で、
合計月3万円の保険料でした。
年収500万円の我が家にとって、
年間36万円の保険料は
老後資産形成をさまたげる大きな負担でした。
ドル型保険の主な問題点は以下の通りです:
- 為替変動により保険料が不安定
- 各種手数料の負担が大きい
(為替手数料、保険関係費用、
解約控除など) - 解約時の元本割れリスク
- 保険と投資が混在し、
どちらも中途半端になりがち
一方、県民共済は皆さんのポストにも
よくチラシが投函されているので
ご存じかもしれませんが、
以下のメリットがあります:
- 月額保険料が安い
(総合保障型で2,000円~4,000円) - 掛け捨て型でシンプルな保障内容
- 必要な保障のみに特化し、
余計な費用がかからない - 年度末決算後に割戻金(余剰金の還付)
(通常8月頃に受け取り)
県民共済の保障内容は掛け捨てながらも
必要十分で、コストパフォーマンスに
優れています。
たとえば総合保障型(月額4,000円)では、
以下のような保障が受けられます:
【県民共済総合保障型の主な保障内容】
- 病気死亡:800万円
- 事故死亡:1,000万円
- 入院(病気):日額10,000円
- 入院(事故):日額10,000円
- 通院(事故のみ):日額1,500円
さらに県民共済の魅力は、
営利を目的としない生協の保険のため、
決算後に剰余金が発生すると
割戻金として還付されることです。
私の場合、
毎年8月頃に約8,000円の割戻金を
受け取っており、
実質的な負担はさらに軽くなっています。
大切なのは、
保険は保険、投資は投資として分けて考える
ことです。
ドル型保険のような貯蓄性保険は、
保険機能と投資機能が混在しているため、
どちらも効率が悪くなりがちです。
たとえば、ドル型保険での積立投資と
NISAでの積立投資を比較すると、
以下のような違いがあります:
ドル型保険での積立
- 各種手数料が高い
(為替手数料、保険関係費用など) - 途中解約時に元本割れのリスク
- 保険と投資が複雑に絡み合い、
効果が見えにくい - 運用商品の選択肢が限定的
NISAでの積立投資
- 運用益が非課税で効率的
- 手数料が安い優良ファンドを選択可能
- いつでも売却できる流動性の高さ
- 運用状況が分かりやすく透明性が高い
県民共済で必要最小限の保障を確保し、
浮いた保険料をNISAで資産運用することで、
より効率的な資産形成が可能になります。
実際に私が見直しを行った結果、
以下のような変化がありました:
【見直し前】
- ドル型保険:月額25,000円
- 医療保険:月額5,000円
- 合計:月額30,000円
【見直し後】
- 県民共済(総合保障型):月額4,000円
- 定期保険(掛け捨て):月額6,000円
- 合計:月額10,000円
定期保険については、
県民共済だけでは死亡保障が不足する場合に
追加で加入しました。
掛け捨て型の定期保険は保険料が安く、
必要な期間だけ大きな保障を
確保できるのが魅力です。
私の場合、
子どもが独立するまでの期間限定で
2,000万円の死亡保障を
月額6,000円で確保しています。
ネット生命保険会社の商品なら、
さらに安い保険料で加入できる場合もあります。
差額:
20,000円の家計改善を実現し、
この全額を老後資産運用に回すことにしました。
【完全ガイド】失敗しない保険見直しの5つのステップ
実際に保険見直しを行う際の
具体的な手順をご紹介します。
私が実践した方法なので、
参考にしていただければと思います。
まず、現在加入している保険の内容を
一覧表にまとめることから始めましょう。
以下の項目を整理してください:
- 保険会社名と商品名
- 月額保険料
- 保障内容(死亡保障、医療保障など)
- 契約期間
- 解約返戻金の有無と金額
次に、本当に必要な保障額を計算します。
一般的な目安は以下の通りです:
- 死亡保障:年収の5~10倍程度
- 医療保障:入院日額5,000~10,000円程度
私の場合、年収500万円なので
死亡保障2,500万円、
医療保障は日額10,000円で
十分と判断しました。
県民共済の各都道府県のホームページで、
お住まいの地域の保障内容と保険料を
確認しましょう。
総合保障型なら月額4,000円で
必要十分な保障が受けられます。
県民共済への加入はとても簡単です。
必要な書類は以下の通りです:
- 加入申込書
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 銀行口座振替依頼書
加入手続きは郵送または
インターネットで完了できます。
審査期間は約1週間程度です。
大切なのは解約のタイミングです。
以下の点に注意してください:
- 新しい保険の保障開始後に解約する
- 解約返戻金の受け取り時期を確認する
- 税務上の影響があるか確認する
私の場合、ドル型保険の解約により
約30万円の解約返戻金を受け取りましたが、
これは一時所得として税務申告が必要でした。
浮いた月2万円は老後資産形成へ
保険見直しで浮いた月2万円は、
全てつみたてNISAでの積立投資に
回すことにしました。
非課税制度を活用した長期投資により、
老後資産形成の確実な第一歩を踏み出せます。
まとめ:保険見直しで実現する効率的な家計管理
保険見直しによる月2万円の家計改善は、
家計全体の効率化への大切な
第一歩となります。
保険と投資を分けて考えることで、
それぞれの機能を最大限活用できるように
なるからです。
今回の見直しで
実現したポイントをまとめると
以下の通りです:
保険の最適化
- ドル型保険から県民共済への切り替えで
大幅な保険料削減 - 必要保障に応じた適切な保険選択
- 掛け捨て型保険で
必要十分な保障を効率的に確保 - 余計な手数料や複雑な仕組みを排除した
シンプルな保障
家計改善の効果
- 月2万円、年間24万円の家計改善を実現
- 保険料負担が家計に占める割合を大幅に軽減
- 浮いた資金で老後資産形成に取り組める
今後の展望
- 保険見直しの成功体験を
他の固定費見直しにも活用 - 携帯電話料金や光熱費なども
見直しでさらなる家計改善 - 確保した資金でつみたてNISAなどを
活用した資産形成
私の経験上、
保険見直しは家計改善の中で
もっとも効果を実感しやすい方法です。
なぜなら、一度手続きをすれば
自動的に毎月の支出が減り、
その効果が継続するからです。
複雑な家計簿をつけ続ける
必要もありませんし、
毎日の節約を意識し続ける必要もありません。
家計改善は一歩ずつ着実に
進めることが大切です。
保険見直しという成功体験を積むことで、
他の固定費見直しにも
自信を持って取り組めるようになります。
携帯電話料金や電気・ガス料金の見直しなど、
さらなる家計改善で老後資産形成を
加速させることも可能でしょう。
今すぐできる第一歩として、
まずは現在の保険証券を引っ張り出して、
月額保険料の合計を計算してみてください。
年収500万円程度の世帯で
月3万円を超えているなら、
見直しのチャンスです。
また、県民共済のチラシが投函されたら、
一度目を通してみることをおすすめします。
保険見直しから始める効率的な家計管理を、
一緒に実践していきましょう。
他の節約術についてはこちらの記事もおすすめです。
注:この記事は筆者の個人的な体験に基づくものであり、すべての方に同様の結果を保証するものではありません。保険の見直しや投資判断は、ご自身の状況をよく確認した上で、必要に応じて専門家にご相談ください。